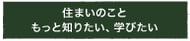高橋修一のエッセイ
上毛新聞 2001年12月26日掲載
「若者の年経た姿を知る」
◎老人とは
「一族を門中(もんちゅう)と呼び、お互いに助け合い、励まし合うこの島の風習は、老人を敬い、老人を大切にする。というよりも、老人の面構えそのものが重厚で、人間としての老いの重さを感じさせてくれる…」
沖縄で、ある人の古希のお祝いに出席した際の石川洋さんの感想である。「親族の代表が老人に酒をくみ、次いで老人がその代表に酒をくみ、一同“おばあちゃんにあやかりますよ”と、一緒にあやかりの杯をいただく…」と続くのだが、老人を大事にしなくなった日本の一昔前の姿を見るようである。
戦後の高度経済成長期を通じて、ともかく金と物質の豊かさを生活の屋台骨に据えてしまったことから、働き手として役に立たぬ高齢者は敬われるどころか、厄介者にすらなったのだが、同時並行的に失われたのは、年経るに従って深まるはずの人間の姿、敬うに足る人間としての面構えであった。
若者は働く機械としてはもはや中古品となってしまった老人を廃品扱いにし、老人はその扱いへのいら立ちをあらわにする。しかし、若者の中に巣食う価値観も、老人を支配してきた内面の価値観も、今となっては同一のものであったかもしれないと、気付くことが必要だ。
最近、二世帯を含む老人同居の家を設計する機会が多い。その際、スッと垣間見せる老人の悲哀の表情を見逃すならば、この設計はきっと失敗に終わるだろう。自分たちのスペースはたっぷりあるというのに、両親用には一部屋あればいいと言う。本人たちもそれで納得していると言うが、両親に問うまでもなく、言葉と老人の思いとは多く裏腹である。こんな時に、私は思うのである。老人とは言っても、元は若者であったのだ。この老人の問題は老いたあなたの問題なのだ…と。老人の姿は若者の生きて年経た姿、老人の皺(しわ)は若者の生きて重ねられた経験のひだのようなものだ。だが、今それが相方に浅く、軽い。
金と物質が何にも増して豊かさの象徴のようになってしまった日本人の人間観、生活観は、すでに反省期にさしかかって久しいと言われながらも、いまだその余韻が覚めやらない。
「俺(おれ)たちァハァ、邪魔もの扱いだァ、あんまり若いもんに迷惑かけないうちにあの世に行っちまった方がいいんだァ…」
時々訪ねる片田舎の村営温泉で、こんなたぐいの言葉をしばしば耳にする。早朝起きて日が暮れるまで野良仕事に明け暮れたかつての若者、老人の営みは、晩年報われぬ形となっている。
人間の晩年はだれにでも訪れるものだ。その期を心おだやかに送るためにも、老いて敬われるような人間観の上に立って今生きているかと問うてみたいものだ。老人の面構えそのものが重厚で、人間としての老いの重さを感じさせてくれる―こうした面構えとは、そのことに気づいた途端に出来上がるといったものではないのだから。